タイトルのとおり、フィット4をデッドニングします。
2020年フルモデルチェンジで発売されたフィット4。
僕もフィット2を乗っており、気にはなっていましたが、同車がブレーキのひきつけで故障(泣)
満を持して購入と相成りました。

前の車両も前ドアのデッドニング、ツイーターを取り付けたオーディオ車両にしていたのですが、新車も同様の改造を施すこととしたのでした。
使用したキットはエーモンさんの音楽計画キット。
目次
1 ドアの内張外し

個人的に一番の難関と思います笑
とにかく、このモデルは最初の取り外しが固い!
要所を書き記しておきたく思います。
まずは、固定ネジとコネクタの取り外しです。

ドア側のひじ掛け部分の上部のプラスチック部分が外れます。
写真のようにマスキングをして、隙間に内張外しを差し込んで外していきます。
これは力も要らず、簡単に外れました。

そしてコネクタを外して・・・

パネル下に固定ネジがあるのでこれを外します。
ドアの内張外しの固定ネジはこの1か所のみとなります。
ネジを外したら、あとはドアの内張を力ずくで外します。
ドアの端部分のプラスチック製のパッキンは、案外外れてくれますが、ドアノブ付近の(中央部分)金属製の留め金具が固いのなんの。
しかしながら、これは力で処理します。
2 デッドニング前処理

なんとか力ずくで外して、ようやく御開帳~
新車なのでキレイです。
実は一度、ドアを外してケンウッド製のスピーカーを取り付け済みです。
とまぁ、デッドニングの話に戻りまして、まずはビニールとブチルゴム除去作業です。
2番目に大変な作業と思います。
ビニールは簡単に取れるが・・・

うまい人はクリーナーをブチルゴムにしみこませて、ビニール側に引っ付けてキレイに剝がすそうな。
僕には・・・無理だ・・・
3 デッドニング工程
それが終わったら、外側パネルを軽く洗浄し(油分を軽く除去)制振材をペタペタ。

その上に吸音材をペタペタ

ブチルゴムの除去が甘々なのはご愛敬。
しかしながら、この後の工程の防音テープやシートの粘着力に影響が出ますので、しっかりと除去しておくべきでした。
そして中の方が終わったならば、締めのサービスホール塞ぎとなります。
型の取り方などは人それぞれ。
僕はサービスホール用のアルミシートのが入っていたビニール袋をサービスホールに当てがって・・・
→穴の形をマジックで書き、
→それをさらにシートに当てて、
→ヘラの圧力でシートに転写、
→それを切り取る
といった要領で形を作っていました。
気持ち大きめにしとけば取り返しのつかないことにはならないし、おおざっぱにスピーディーにいきまっしょい!

二つの大きなサービスホールと塞いでも良い小さな穴を防音テープで塞いだ状態。
右側の配線を逃がすところは妥協して、穴を完全に塞ぎませんでした。
大丈夫・・・だよね??
指で軽くコンコン、と叩いてみて響くような場所があれば、さらに防音テープを張って響かないように補強していきました。
最後に内張を取り付けて終了となりますが・・・

内張のこの白いプラスチック部分がサービスホールを塞いだ防音テープに干渉しそうなので、思い切って除去してしまいます。
これはペンチなどで丁寧に除去。
無理に捻じ曲げて除去しようとすると、内張の表面側にプラスチックの傷みが出てしまう恐れがあるので注意です。

4 終了、ビフォーアフター
と言いつつ、ビフォーがありませんです。
申し訳ない。
しかし、ドアを外からたたいた時の響きが全くもってない感じ。
ドアを閉めた音や、もちろんオーディオの低音出力にも寄与してくれることでしょう。


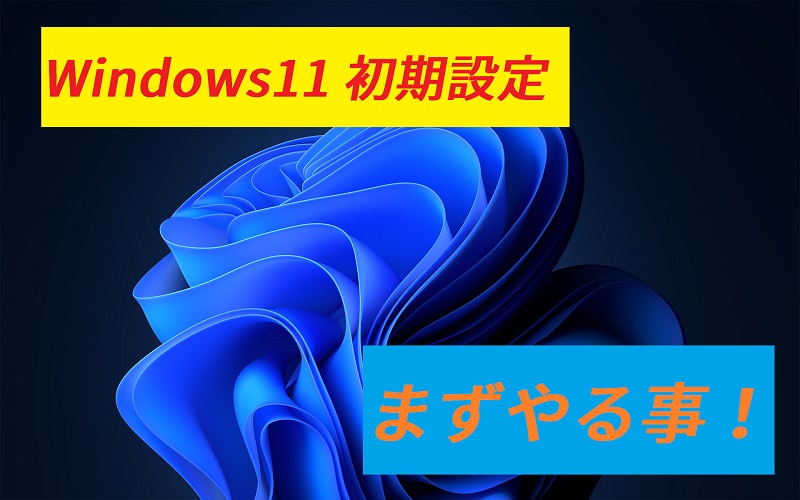






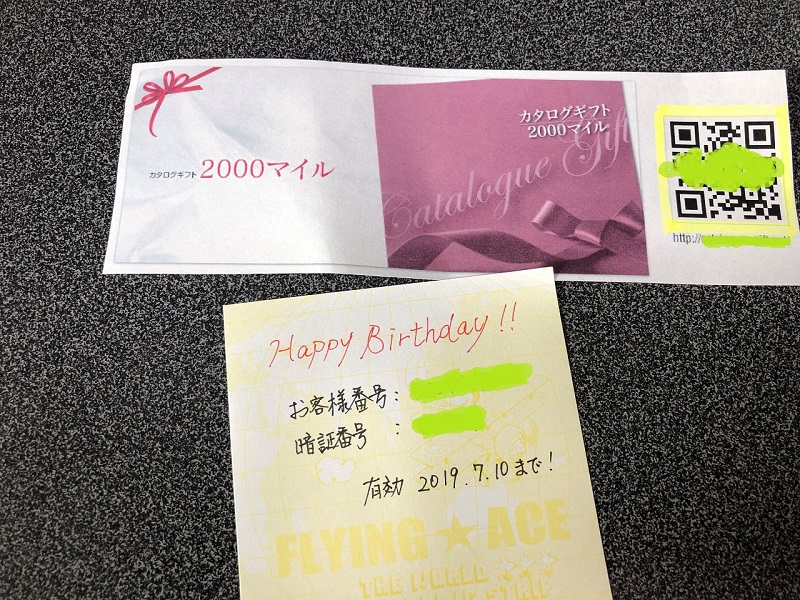

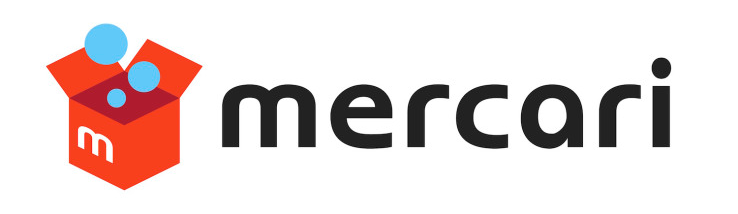







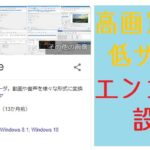


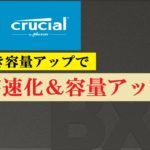
最近のカーオーディオ用スピーカーを見て気になることがありましたのでこちらに書かせていただきます。
最近のスピーカーは昔のスピーカーに比べてものすごく広帯域になっているように表示されています。
これは測定基準が異なるためでそのままの比較は不適当、特にカーオーディオ用は酷いように思います。
オーディオ関連の特性表示が特に厳密だった時代の周波数特性は±3dBになっています。例えば
https://audio-heritage.jp/JBL/speaker/4343.html
基準周波数(うろ覚えですが1KHzだったと思います)との音量差が2倍~半分の範囲という意味です。
3dB=0.3B(dは十分の一を表します)・・・10の0.3乗≒2 +3dBは2倍、-3dBは2分の1
現在のカーオーディオ用スピーカーの例として上のスピーカーとカタログ上の低域再生限界が近いのが
https://www.kenwood.com/jp/car/speakers_amplifiers/custom-fit-speakers/products/kfc-xs174s/spec/
こちらは-10dBですので、10の-1乗・・・0.1(10分の1)までを再生帯域扱いしています。
ですので、表示してあるような音域はかなりブースとしないと感じ取れないはずです。
ちなみに、スピーカーの能率の3dBの違いはアンプの出力が2倍違うことに相当します。
ほかに数年前から流行っているハイレゾに関して、昔のアンプやスピーカーも今でいう「ハイレゾ」です。
CDの規格策定時に、データ量の関係などから20~20KHzと制限されただけです。
ですから録音機器・編集機器などであればハイレゾ対応かどうかは性能を左右しますが
スピーカーやヘッドホン、アンプなどに関しては基本としてハイレゾは関係ありません。
あと、PC関係で「真空管を使ったアンプ」と表示されているものの大半はインチキだと思います。
理由は真空管の電力消費・発熱・出力インピーダンスなどの問題を無視したようなスペックだからです。
オーディオ関係の話は切りがありませんので、一旦この辺まで。